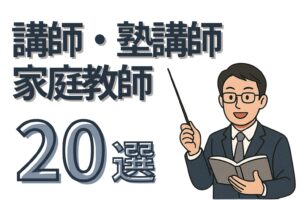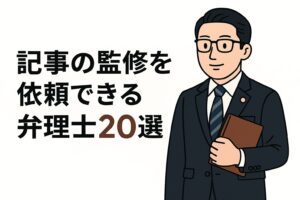法律関連の記事を公開する際には、専門知識に裏打ちされた正確さと信頼性が欠かせません。
しかし、膨大な弁護士の中から自社記事に最適な監修者を見つけるのは難しいものです。
本記事では、企業法務から知的財産、労働・消費者問題まで幅広いテーマに対応できる弁護士20名を厳選し、得意分野や料金目安とともにご紹介します。編集・広報担当の方がリーガルチェック先を探す際の手掛かりとして、ぜひご活用ください。
※本記事は 2025年5月1日時点の情報に基づいて作成しています。最新の状況は各事務所の公式サイト等でご確認ください。
依頼できる弁護士一覧
以下に、記事監修を依頼できる主な弁護士を20名以上ピックアップし、その事務所名または個人名、得意分野、対応地域、監修料金目安、特記事項(経歴や実績)をまとめました。
 吉原綜合法律事務所企業研修・広告法務チェック実績豊富。監修費用:16,500円
吉原綜合法律事務所企業研修・広告法務チェック実績豊富。監修費用:16,500円 ジン法律事務所弁護士法人1万字まで22,000円。初回5,000円キャンペーン。監修費用:22,000円
ジン法律事務所弁護士法人1万字まで22,000円。初回5,000円キャンペーン。監修費用:22,000円 牛島総合法律事務所大手。M&A・危機管理実績。ビジネス誌執筆多数。監修費用:応相談
牛島総合法律事務所大手。M&A・危機管理実績。ビジネス誌執筆多数。監修費用:応相談 プロスパイア法律事務所ブロックチェーン・インフルエンサー法務の最先端領域。監修費用:応相談
プロスパイア法律事務所ブロックチェーン・インフルエンサー法務の最先端領域。監修費用:応相談 法律事務所アルシエンネット誹謗中傷対策専門。SNSリスク記事監修実績。監修費用:応相談
法律事務所アルシエンネット誹謗中傷対策専門。SNSリスク記事監修実績。監修費用:応相談 弁護士法人GVA法律事務所薬機法・景表法など広告規制・医療法務に強み。監修費用:応相談
弁護士法人GVA法律事務所薬機法・景表法など広告規制・医療法務に強み。監修費用:応相談 AZMORE国際法律事務所日中クロスボーダー法務・知財に精通。監修費用:応相談
AZMORE国際法律事務所日中クロスボーダー法務・知財に精通。監修費用:応相談 トップコート国際法律事務所フィンテック・暗号資産法務を得意。監修費用:応相談
トップコート国際法律事務所フィンテック・暗号資産法務を得意。監修費用:応相談 長崎国際法律事務所国際企業法務と知財。投資詐欺記事監修経験。監修費用:応相談
長崎国際法律事務所国際企業法務と知財。投資詐欺記事監修経験。監修費用:応相談 立川法律事務所不当解雇等実績豊富。複数拠点で緊急チェック対応。監修費用:応相談
立川法律事務所不当解雇等実績豊富。複数拠点で緊急チェック対応。監修費用:応相談 六甲法律事務所関西で労務案件豊富。上場企業法律記事監修担当。監修費用:応相談
六甲法律事務所関西で労務案件豊富。上場企業法律記事監修担当。監修費用:応相談 弁護士法人浅野総合法律事務所自社労働メディア運営し代表自ら執筆・監修。監修費用:応相談
弁護士法人浅野総合法律事務所自社労働メディア運営し代表自ら執筆・監修。監修費用:応相談 弁護士法人プラム綜合法律事務所労働問題豊富。目安44,000円/記事。監修費用:応相談 DR:26
弁護士法人プラム綜合法律事務所労働問題豊富。目安44,000円/記事。監修費用:応相談 DR:26 林たかまさ法律事務所(PLeX法律事務所)労働者側に注力。法律コンテンツ作成を専門とし発信力高い。監修費用:応相談
林たかまさ法律事務所(PLeX法律事務所)労働者側に注力。法律コンテンツ作成を専門とし発信力高い。監修費用:応相談 スタートビズ法律事務所IT企業の労務法務支援・スタートアップ人事労務記事監修多。監修費用:応相談
スタートビズ法律事務所IT企業の労務法務支援・スタートアップ人事労務記事監修多。監修費用:応相談 日暮里中央法律会計事務所弁護士と税理士共同運営。弁護士ほっとライン相続記事監修実績。監修費用:応相談
日暮里中央法律会計事務所弁護士と税理士共同運営。弁護士ほっとライン相続記事監修実績。監修費用:応相談 弁護士法人ネクスパート法律事務所全国展開。ベンナビ相続コラム監修者多数在籍。監修費用:応相談
弁護士法人ネクスパート法律事務所全国展開。ベンナビ相続コラム監修者多数在籍。監修費用:応相談 川崎相続遺言法律事務所相続専門を掲げ、税理士資格も有する代表。ベンナビ相続コラム監修実績多数。監修費用:応相談
川崎相続遺言法律事務所相続専門を掲げ、税理士資格も有する代表。ベンナビ相続コラム監修実績多数。監修費用:応相談 リーガルプラス法律事務所相続トラブル専門。公式サイトコラムを弁護士が監修。監修費用:応相談
リーガルプラス法律事務所相続トラブル専門。公式サイトコラムを弁護士が監修。監修費用:応相談
※上記の監修料金はあくまで目安です。正式な料金は依頼内容や弁護士の規定によって異なるため、事前に各弁護士事務所へお問い合わせください。
基礎知識
弁護士とは?専門領域と監修できるテーマ
弁護士は、高度な法律知識と資格を持ち、法律事務を代理・支援できる法律の専門家です。日本では司法試験合格後、所定の研修を経て弁護士資格が与えられます。弁護士ごとに得意分野があり、企業法務、労働問題、離婚・相続、知的財産、刑事事件など様々な専門領域に分かれています。
記事の内容に応じて、該当分野に強い弁護士に監修を依頼すると良いでしょう。例えば企業法務に関する記事であれば企業法務専門の弁護士、離婚問題の記事であれば家事事件に詳しい弁護士といった具合に、テーマにマッチした弁護士が適切な監修を行ってくれます。
弁護士による記事監修では、記事中の法律解釈や事実関係について誤りがないかチェックしてもらえます。また、記事テーマによって必要となる法律上の注意事項(例えば景品表示法や著作権法、労働基準法など)についても専門的観点から助言を受けることができます。その結果、法律面で正確かつ信頼性の高い記事内容に仕上げることが可能です。
弁護士に監修を依頼するメリット
法的リスクの排除
弁護士に記事内容をチェックしてもらうことで、法律違反や読者への誤解を招く表現を未然に防げます。例えば誹謗中傷やプライバシー侵害、著作権侵害のおそれがある記述を指摘してもらえれば、公開前に修正することでトラブル発生を防止できます。これは企業にとって法的リスクの低減につながります。
内容の信頼性向上
専門家である弁護士が監修した記事であることを明示すれば、読者に与える信頼感が増します。法律のプロのお墨付きがあることで記事全体の権威性が高まり、メディアや記事の信用度アップに寄与します。
誤情報の訂正
法律に関する内容は一般のライターだけでは誤りに気づきにくいものです。弁護士監修により、条文の適用誤りや最新判例の見落としといったミスを正せます。その結果、正確で質の高いコンテンツ提供が可能になります。
読者満足度の向上
法律問題は読者からの質問やクレームにつながりやすい分野ですが、監修を受けた記事であれば内容の明確さや根拠の提示が適切になされており、読後の満足度が高まります。専門的で難解なテーマでも、弁護士が噛み砕いて解説ポイントを補足してくれることで読みやすくなる効果も期待できます。
主なサービス内容と料金相場
主なサービス内容
記事監修を依頼した場合、弁護士は記事原稿を読み込み、法律面での誤りや不適切な表現がないかをチェックしてくれます。具体的には、関連法令の引用ミスや解釈の誤りの訂正、読者に誤解を与えうる表現の修正提案、事実関係についての裏付け確認、必要に応じた注意書きや免責事項の追記アドバイスなどが含まれます。
また、記事全体の構成や論調について法律家の視点からコメントをもらうこともできます。場合によっては、監修した弁護士の名前を記事末尾に「監修:〇〇弁護士」のように記載し、読者に対して監修済みである旨を示す対応も行われます。
料金相場(1万~10万円)
弁護士による記事監修の費用は、記事の長さや難易度、求めるチェックの範囲によって大きく異なります。相場感としては、短い記事(数千文字程度)であれば1〜3万円程度から、専門性が高く調査が必要な記事や長文記事では5〜10万円以上になるケースもあります。
また、時間単価で料金設定されることもあり、弁護士の時間当たり料金は1〜3万円前後が一般的です。著名な弁護士や難易度の高い案件ではそれ以上の報酬となる場合もあります。具体的な監修料は依頼前の相談で見積もりを出してもらえるので、予算と照らし合わせつつ依頼先を検討すると良いでしょう。なお、多くの弁護士事務所では初回相談は無料だったり、簡易な記事チェックであれば定額パック料金を設けている場合もあります。
お役立ち情報
依頼から公開までの流れ
弁護士に記事監修を依頼してから記事が公開されるまでの一般的な流れを説明します。
- 弁護士の選定と相談
まず記事の内容に適した専門分野を持つ弁護士を探し、メールや電話でコンタクトを取ります。記事の概要や分量、監修の目的を伝え、監修可能か打診しましょう。その際に簡単な見積もりやスケジュール感も確認します。 - 正式依頼と契約
監修を引き受けてもらえることになったら、正式に依頼します。必要に応じて業務委託契約書や秘密保持契約(NDA)を交わし、監修料や納期など条件を明確に定めます。 - 記事原稿・資料の送付
弁護士にチェックしてもらう記事の原稿を送付します。下書き段階でも構いません。また、記事執筆時に参考にした資料や、弁護士に特に見てほしいポイントをまとめたチェック指示書があれば一緒に添付します。 - 弁護士による監修作業
弁護士が記事内容を精査します。法律的に誤りがないか、読者に誤解を与える表現はないか、関連する最新の法改正や判例を反映できているかなど、多角的にチェックが行われます。必要に応じて記事内にコメントや修正提案が挿入され、フィードバックが返ってきます。 - 修正対応と質問確認
弁護士からのフィードバックをもとに、ライターや編集者が記事を修正します。不明点があれば弁護士に質問し、追加で確認を取ります。このやり取りを経て記事内容を確定させます。 - 最終確認と公開許可
修正後の最終稿を弁護士に再度チェックしてもらい、問題がなければ「監修済み」として完了となります。弁護士から公開許可(了承)を得たら、記事をウェブサイトなどに公開します。公開時には監修者として弁護士名を明記することで、読者にも専門家チェック済みであることが伝わります。
このように、依頼から公開までには①弁護士探し→②打診・契約→③原稿送付→④チェック→⑤修正対応→⑥最終確認・公開というステップを踏みます。記事のボリュームにもよりますが、全体で数日〜数週間の期間を見込んでおくと良いでしょう。
依頼メール・チェック指示書テンプレート
記事監修を依頼する際のメール文面と、弁護士に伝えるべきポイントをまとめたチェック指示書のテンプレート例です。必要に応じて自由にカスタマイズしてください。
依頼メール(テンプレート)
件名:記事監修のご依頼(「○○」に関する記事)
〇〇法律事務所
〇〇先生
初めまして。△△(会社名またはメディア名)の□□と申します。突然のご連絡にて失礼いたします。
現在、当方にて「○○(記事テーマ)」に関する記事を作成しており、法律面の内容確認(リーガルチェック)をお願いできる弁護士の先生を探しておりまして、ご専門分野である〇〇にお詳しい〇〇先生に是非監修をお願いしたくご連絡いたしました。
【依頼内容】
・記事タイトル:「○○」(仮)
・文字数:約△△△△字(A4換算△ページ程度)
・記事の概要:○○について、一般読者向けに解説する内容です。□□法や■■法の解釈に触れており、法律的に正確な内容にしたいと考えております。
【お願いしたい事項】
・記事全体をお読みいただき、法律的な誤りや表現の適否をご指摘ください。特に、△△法の解釈部分と判例の引用部分を重点的に確認いただきたいです。
・必要に応じて読者に注意を促す注記や補足すべき情報があればご教示ください。
【スケジュール】
・〇月〇日(〇)までに初稿をチェックいただき、フィードバックをいただけますと幸いです。タイトな日程で恐縮ですがご対応可能でしょうか。納期のご希望がございましたら調整いたします。
【報酬】
・監修料として¥○○○○を予定しております(記事分量とお願い内容に応じてお見積もりいただければ幸いです)。お支払い条件などご指定ございましたらお知らせください。
本メールに記事の原稿(下書き段階)と簡単なチェック項目リストを添付いたしました。ご多忙のところ恐れ入りますが、ご検討のほど何卒よろしくお願いいたします。
(御礼・署名)※上記メールでは、件名で「記事監修のご依頼」であることを明示し、本文で依頼背景→依頼内容詳細→確認事項→スケジュール→報酬の順に簡潔に伝えています。初めて依頼する弁護士には自己紹介も添え、なぜその弁護士に依頼したいのか(専門分野など)触れると丁寧です。
チェック指示書(テンプレート)
依頼メールとは別に、記事原稿と一緒に渡す「チェック指示書」を作成すると、弁護士が効率よくポイントを把握できます。以下はそのテンプレート例です。
【記事タイトル】「○○について」
【想定読者】法律の専門知識がない一般読者
【記事の狙い・コンセプト】○○について基本的な知識をわかりやすく解説し、読者の△△に役立ててもらう。
【特にチェックしていただきたい点】
1. △△法と□□法の適用関係についての記述(第2章):解釈に誤りがないか。
2. 最近の判例紹介部分(第3章):判決内容の要約が正確か。
3. 表現の妥当性:読者に誤解を与える恐れのある表現はないか(特に「違法」「絶対」など強い表現)。
【参考資料】判例X(○年○月○日 最高裁)全文、△△省ガイドライン(URL)、統計データ(添付PDF)
【その他】専門用語には簡単な説明を付記していますが、不十分な場合はご指摘ください。判例名や条文番号の表記ゆれなども適宜修正いただけますと幸いです。
以上、よろしくお願いいたします。このように、記事の概要や読者層、チェックしてほしいポイントを箇条書きにして添えることで、弁護士がスムーズに監修作業に入れます。特に法律解釈や数字データの部分はミスが生じやすいので具体的に示しておくと良いでしょう。
よくある質問
- どのタイミングで弁護士に依頼すれば良いですか?
-
記事の草稿が完成した段階で依頼するのが一般的です。執筆途中よりも、一通り書き上げてからの方が弁護士も全体像を把握しやすく効率的です。ただし執筆前に概要だけ相談し、方向性にアドバイスをもらうケースもあります。また、法改正の直後など内容に不安がある場合は早めに相談すると良いでしょう。
- 一度依頼したら、その後の質問対応も全て料金に含まれますか?
-
基本的な軽微な質問であれば監修料に含まれることが多いですが、範囲を超える追加対応は別料金になることがあります。契約時にどこまでを範囲とするか確認しておきましょう。
通常、初回のフィードバックに対する修正確認程度であれば追加料金なしで対応してくれる場合が多いです。しかし、大幅な加筆や新たな論点の調査を依頼する場合は追加報酬が発生し得ます。
- 監修してもらった記事に弁護士の名前を出す必要はありますか?
-
必須ではありませんが、可能であれば記名してもらうのがおすすめです。監修者名を明記することで記事の信頼性が高まります。ただし、弁護士側が匿名を希望する場合もあるため、名前を出してよいか事前に確認しましょう。名前を出さない場合でも「弁護士監修済み」といった表記で監修済みであることを伝えることがあります。
- 監修を受ければ法的責任は弁護士に移りますか?
-
いいえ、記事内容の最終的な責任は執筆者・発行者にあります。弁護士はあくまで助言者であり、監修を受けたからといって法的トラブルに対する完全な免責になるわけではありません。もっとも、弁護士のチェックを経ていれば重大な誤りは通常なくなるため、リスクは大幅に減少します。
必要に応じて「本記事の内容については十分注意を払っていますが、最終的な判断は読者ご自身でお願いします」等の免責文を記事に入れることも検討してください。
- オンラインで全国の弁護士に依頼できますか?
-
はい、メールやオンライン会議を活用すれば全国どこからでも依頼可能です。監修作業は原稿のやり取りが中心なので、直接対面せずとも問題ありません。ただし、ローカルな条例や慣行に詳しい地元の弁護士に頼みたい場合は、その地域の弁護士会を通じて紹介を受ける方法もあります。最近ではZoom等で打ち合わせを行い、メールでフィードバックを受け取るケースが増えています。
まとめ
専門分野を持つ弁護士に監修を依頼すれば、法的リスクを抑えつつ記事の説得力を大幅に高められます。今回取り上げた弁護士はいずれも豊富な実務経験とメディア対応実績を備え、オンラインでの依頼にも柔軟に応じてくれる点が魅力です。
依頼時には記事概要やスケジュール、予算を具体的に伝え、相性のよいパートナーを見つけてください。専門家の知見を得たコンテンツが、貴メディアの信頼性と読者満足度をさらに高める一助となれば幸いです。
関連リンク